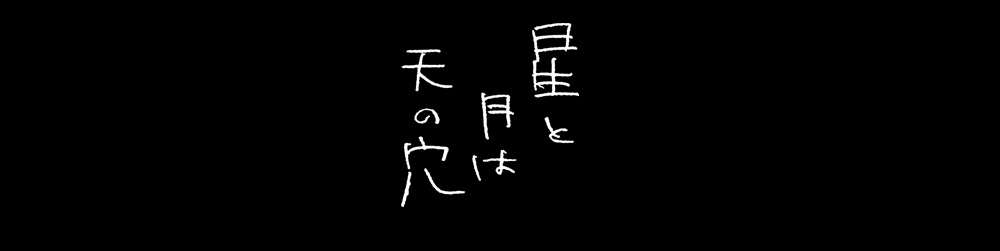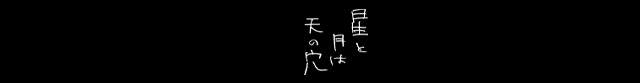NEWS
日本映画界を代表する脚本家・荒井晴彦と時代の歩み
『赫い髪の女』『Wの悲劇』『ヴァイブレータ』『大鹿村騒動記』『共喰い』・・・
映画とともに歩み続けた脚本家人生、そして監督としてついに念願の企画を映画化。
 手がけてきた作品名だけで日本映画史を辿るようなラインナップだ。
手がけてきた作品名だけで日本映画史を辿るようなラインナップだ。
「愛と性」に正面から向き合い、人間の本質に迫るような鋭い視点で描き出す。弱さやどうしようもなさ、そして強さを秘めた“人間”の可能性を愛してやまない、そんな豊かさに満ちた作品が溢れている。
荒井晴彦、1947年生まれの78歳。足立正生の鉛筆削り、ピンク映画の助監督、田中陽造の清書係を経て、1977年『新宿乱れ街 いくまで待って』で脚本家デビュー。以来脚本家として、そして1997年『身も心も』からは監督としても映画界で半世紀に渡り活躍。そのフィルモグラフィーは日本映画史と重なるだけでなく、その時代の空気感、そこに生きる人間をスクリーンに封じ込めたような生々しさがある。同時に、それを演じてきた俳優たちをも1つ上のステージへと押し上げる、そんな作品群が並んでいる。
<70年代:実験精神に溢れたロマンポルノ時代>
「10分に1回の濡れ場」「上映時間は70分程度」「本番なし」の条件のもと、実験精神に溢れた作品を生み出し続けた日活ロマンポルノ。
荒井は、神代辰巳、藤田敏八、根岸吉太郎ら、日本映画界の名監督たちと脚本家としてともに駆け抜けた。特に『赫い髪の女』(神代辰巳監督/79)は荒井の初期の代表作として、またロマンポルノを代表する1作として、そして主演した宮下順子の出世作としても愛され続ける作品。中上健次の「赫髪」を原作に、ダンプカーの運転手の主人公と、道で拾った赫い髪の女との濃密でただれた愛欲のうねりを描く。時を経て作品は海を渡り、現在海外からも高い評価を得ている。
<80年代:メディアミックス、角川映画の時代>
メディアミックスの時代が到来。その旗手が角川映画だ。
アイドル映画を中心にプログラム・ピクチャーが量産された時代。薬師丸ひろ子、原田知世らがスターとして数々の作品の主演を飾る中登場したのが『Wの悲劇』(澤井信一郎監督/薬師丸ひろ子主演/1984年)。荒井の提案で原作から設定を変更。女優を目指す劇団の研究生がある事件に巻き込まれながらのし上がっていくストーリーの中で、主人公と演じる役、二人の女性が重なる二重構造となった。アイドルだった薬師丸ひろ子を俳優として映画同様大きく飛躍させた作品のひとつであり、「顔ぶたないで、わたし女優なんだから」など、印象的なセリフが今も多くの人の心を掴んで離さない。
<00年代:時代の空気が変わり、映画も変わっていく>
バブル崩壊後経済的な低迷も続き、社会的にも閉鎖的な空気が漂い始めた時代。
『ヴァイブレータ』(廣木隆一監督/2003年)では、アルコール依存の女性ルポライターと長距離トラック運転手のゆきずりの愛を描いた。トラウマを抱え、うまく人間関係を構築できない主人公。そこには現代を生きる人間の姿が凝縮されており、映画のルックも殺伐とした空気が漂う。それでも互いの体が、存在が、温度が心を癒すというストーリーは時代の“気分”を象徴していた。主演は寺島しのぶ、共演に大森南朋。寺島にとっては初の主演作にして、日本映画界に欠かせない女優として一気に名を上げた1作だと言えるだろう。
<10年代:映画の環境が大きく変化した時代>
映画館は急速にデジタル化、35mmフィルムからDCPへと変わっていった。
さらにはスマホが急速に普及したことで、誰もが“撮影”できるようになった。ドローンが登場したのもこの頃で、デジタル撮影が主流化、制作現場、映画館ともに大きな変化があった時代だ。荒井は原田芳雄の遺作ともなった『大鹿村騒動記』(2011年/阪本順治監督)で笑いあり、涙ありのハートフルな人間ドラマを描いてみせる。300年続く大鹿歌舞伎の伝統を守る美しい景観の村で起こる騒動。そこには温かい人間の“手触り”がある。
一方で、2年後『共喰い』(2013年/青山真治監督)を発表。血、因縁、そして時代の終わり。昭和63年の山口県下関を舞台にしたこの映画は、単に昭和時代の終わりを描くだけでなく、男性優位の社会構造の中で女性がさまざまな痛みを経験する一方、男性が快楽や利益を得ていた時代の終わりを示唆するものでもあり、2025年現在、さらにそうした価値観のアップデートが進む現代に繋がる。この作品で主演の菅田将暉は映画界で一気に花開いていく。
<2025年:昭和レトロの世界観。クラシカルな作品を新しく見せる「星と月は天の穴」>
 時代時代の空気とそこに生きる人間の姿を描いてきた荒井晴彦が、脚本のみならず監督として手がける最新作は、自身が18歳の時に出会い「映画の仕事を始めてからは、いつかやりたいと思っていた」吉行淳之介の「星と月は天の穴」。50年来の念願の企画だ。
時代時代の空気とそこに生きる人間の姿を描いてきた荒井晴彦が、脚本のみならず監督として手がける最新作は、自身が18歳の時に出会い「映画の仕事を始めてからは、いつかやりたいと思っていた」吉行淳之介の「星と月は天の穴」。50年来の念願の企画だ。
いわく、「彼女もいないし、女の子の手を握ったのは高校の文化祭のオクラホマミキサーの時だけだった。それもそっと」。いわば、純朴な男子だった 1966 年当時の荒井青年に、『群像』新年号に掲載された吉行淳之介の小説「星と月は天の穴」は、鮮烈すぎるほどの衝撃をもたらした。「まだ想像でしか“女性というもの”を知らなかった当時の自分は、想像で欲情するこの描写に、性には“想像”が必要なんだ、味付けみたいなものが必要なんだ、と分かったような気がしたんです。吉行さんの小説は、実は女性を描いているようで女性に対する自分を、男の悲しさや滑稽さ、女性との距離感を描いているんですよね」と、吉行の小説に魅せられた理由を明かす。
普段脚本家として原作を脚色する際は「脚色は原作に対するクリティーク(批評)だ」という、田村孟(「白昼の通り魔」「新宿泥棒日記」「少年」などを手掛けた脚本家)の言葉をモットーにして、原作を批評するように欠点を探し、描かれてないことを足していくという荒井だが、今回はほぼ忠実に設定やセリフを脚本に落とし込んでいる。それも原作を愛するがゆえ。
「妻に裏切られ、愛とか恋とかいう情感を持ち込むのを拒否し、女を“道具”として扱おうと思っている男が“道具”に敗けていく小説」と荒井は語るが、急速に価値観がアップデートされていく現代でこそ、生まれるべくして生まれた映画だと言えるだろう。