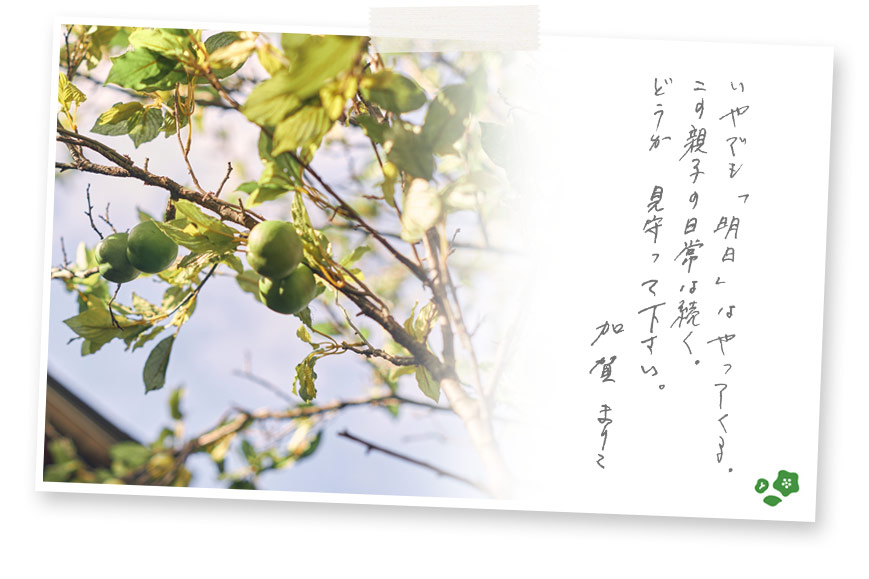イントロダクション
イントロダクション
一緒に笑って、たまに怒って涙して。
このありふれた毎日が宝物。
このありふれた毎日が宝物。
都会の古民家で寄り添って暮らす母と息子。ささやかな毎日を送っていたが、息子が50回目の誕生日を迎えた時に母はふと気づく。「このまま共倒れになっちゃうのかね?」
母親と自閉症を抱える息子が、社会の中で生きていく様を温かく誠実に描く本作。包容力あふれる母親を演じるのは、54年ぶりに主演を務める加賀まりこ。軽口を叩きながらも、小柄な身体で大きな息子の世話をする姿はとてもチャーミング。だからこそ、やがて訪れる“息子が1人で生きる未来”を案ずる横顔が、より一層切ない。息子役にはNHK連続テレビ小説「おちょやん」など俳優としても活躍中の塚地武雅(ドランクドラゴン)。地域コミュニティとの不和や偏見といった問題を取り入れながらも、親子の絆と深い愛を描き、あたたかな感動をもたらす。
母親と自閉症を抱える息子が、社会の中で生きていく様を温かく誠実に描く本作。包容力あふれる母親を演じるのは、54年ぶりに主演を務める加賀まりこ。軽口を叩きながらも、小柄な身体で大きな息子の世話をする姿はとてもチャーミング。だからこそ、やがて訪れる“息子が1人で生きる未来”を案ずる横顔が、より一層切ない。息子役にはNHK連続テレビ小説「おちょやん」など俳優としても活躍中の塚地武雅(ドランクドラゴン)。地域コミュニティとの不和や偏見といった問題を取り入れながらも、親子の絆と深い愛を描き、あたたかな感動をもたらす。


 ストーリー
ストーリー
父親代わりの梅の木が運んでくれた“小さな奇跡”とは・・・
山田珠子は、息子・忠男と二人暮らし。毎朝決まった時間に起床して、朝食をとり、決まった時間に家を出る。庭にある梅の木の枝は伸び放題で、隣の里村家からは苦情が届いていた。ある日、グループホームの案内を受けた珠子は、悩んだ末に忠男の入居を決める。しかし、初めて離れて暮らすことになった忠男は環境の変化に戸惑い、ホームを抜け出してしまう。そんな中、珠子は邪魔になる梅の木を切ることを決意するが・・・。
ことわざ「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」とは?
樹木の剪定には、それぞれの木の特性に従って対処する必要があるという戒め。転じて、人との関わりにおいても、相手の性格や特徴を理解しようと向き合うことが大事であることを指す。


 キャスト
キャスト

山田珠子役 加賀まりこ

山田忠男役 塚地武雅

里村茂役 渡辺いっけい

里村英子役 森口瑤子

里村草太役 斎藤汰鷹

大津進役 林家正蔵

今井奈津子役 高島礼子

 スタッフ
スタッフ

監督・脚本: 和島香太郎
1983年生まれ、山形県出身。テレビドラマ「東京少女」「先生道」などの演出を手掛ける。2012年、短編『WAV』がフランス・ドイツ共同放送局 arte「court-circuit」で放送。また詩人黒田三郎の詩集を原作とした短編『小さなユリと/第一章・夕方の三十分』がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭短編部門にて奨励賞受賞。2014年、初監督作『禁忌』が劇場公開。その他、脚本を担当した『欲動』、『マンガ肉と僕』が釜山国際映画祭、東京国際映画祭に出品。2017年1月より、ネットラジオ「てんかんを聴く ぽつラジオ」(YouTubeとPodcast)を月1回のペースで制作・配信。てんかん患者やそのご家族をゲストに招き、それぞれの日常に転がっている様々な悩みと思いを語ってもらっている。

 監督インタビュー
監督インタビュー
- ――この作品を作ろうと思った経緯を教えてください
- 数年前、あるドキュメンタリー映画に編集として関わった経験が反映されています。自閉症の男性の一人暮らしを描いた映画です。膨大な量の映像素材には、福祉サービスの方や親族との交流が記録されていました。しかし、隣家の人が写りそうになると、それを避けるようにカメラがブレる。その人は度々苦情を言いに来る方でした。自閉症を原因とする予測のつかない言動によってトラブルが繰り返されており、隣家との関係は良好ではなかったのです。しかし、男性が地域の中で孤立していることは見逃せませんでした。近隣住民の視点を取り入れるために取材を申し込んだこともありますが、出演は断られ、カメラを向けることはできませんでした。こうした軋轢について、男性のお母様はどのように向き合ってきたのか。すでに他界されていたのでお話を伺うことはできませんでした。ですが、フィクションであれば近隣住民との軋轢や、出会えなかったお母様の本音を表現できるのではないかと思いました。共生への願いも含まれていますが、押しつけがましくならないように、ささやかな出来事の積み重ねを描きました。
- ――キャスティングについて、お聞かせください
-
珠子は占い師として客の悩みを聞く存在です。助言を与える様子は、自分の半生を振り返りながら過去に向かって語りかけているようにも見えます。率直だけど包容力があり、女性ファンが多い。そのイメージは、物おじせずに言いたいことをおっしゃる加賀さんの印象と合致しました。うちの近所にもお婆さんが営む占いの館があるので、取材を兼ねて手相と人相を見てもらったことがあります。「あんた映画監督って柄じゃないよ」、「今から理数系の研究職に就いた方がいい」と散々な言われようでしたが、占い師のお婆さんも認知症の旦那さんを看取った時のことを話してくれて、気づいたら3時間くらい経っていました。占いを通して自分の孤独や痛みと向き合ってきたのかもしれません。その生き様は珠子とも重なります。加賀さんは、自閉症の方を育ててきた親御さんを身近で見てこられたので、当事者に強い尊敬の念を持っていました。シナリオを見る目は厳しいですが、珠子という役を掘り下げていく上で加賀さんの意見には大きな影響を受けています。修正したシナリオを送るとすぐに電話をくださって、「あんた直すの下手ね~」とダメ出しが始まります。自分は感情を台詞で表現するのが苦手ですが、それも見抜かれていました。「恥ずかしがってちゃダメ」、「言葉にしないと伝わらないんだから」と、まるで劇中の人生相談のようでした。そうしたプロセスを経て加賀さんへの信頼が深まったように思います。実は決定稿が出来るまで出演の承諾は得られなかったのですが、最終的には「うん」と言っていただけたのでほっとしました。
忠さんのイメージを考える上では、自閉症の方の親御さんのお話が参考になりました。「自閉症の方は社交性がなく、自分の殻に閉じこもっていると言われがちだけど、実際は人のことをとてもよく見ていて、人に対する独特のこだわりを持っている」。塚地さんも人の気持ちの動きを全身で感じ取る方だと思います。 以前、取材のために訪れたグループホームで、そこに入居されている自閉症の男性とお話をさせていただいたことがあります。その男性は、どこかで聞いたと思われるアナウンスを真似されていました。何を言っているのかを聞き取ろうとする自分とは対照的に、塚地さんは「女性の声かなぁ」と呟いたんです。声色だけで女性のアナウンスを真似ていることに気づいたようです。でも それ以上の詮索はせず、静かに見守っていました。女性のアナウンスが流れる風景や、男性の思い入れの深さを想像していたのかもしれません。その鋭敏な感覚と、人への関わりの繊細さは、自閉症の方の世界を表現する上で大切な資質だと思います。また、空気感にも敏感な方です。撮影現場では自分の焦りや苛立ちを簡単に見抜かれ、声をかけていただいたこともあります。監督は俳優に見られる仕事でもあるということを塚地さんとの関わりを通して学ばせていただきました。
- ――前作「禁忌」を経ての転機と変化があれば教えてください
- 『禁忌』で描いたのは、社会的に絶対悪とされる人たち、感情移入が困難とされるタイプの人たちです。欲望そのものを否定される人間の葛藤を描きたいと思いましたが、想像だけで組み立てたシナリオでは、実感の伴う演出ができませんでした。取材が足りず、当事者性を欠いたことを反省しています。厳しいお言葉もいただきました。 その後に作り始めたのが、てんかん患者の悩みについて語るネットラジオ「ぽつラジオ」でした。自分にはてんかんという持病があります。社会の偏見もあるので「病気のことは伏せた方がいい」と言われて育ちました。映画の現場でも隠していましたが、撮影が進むに連れて疲労や睡眠不足が蓄積し、発作のリスクが高まっていくことが不安でした。映画を作り続けるためには、てんかんのリスクをスタッフに知ってもらう必要があり、その責任からは立ち去れないと思いました。そして、切羽詰まった自分の悩みを聞いてくれたのが他のてんかん患者たちでした。似た境遇にある彼らもまた、てんかんを伏せて社会に溶け込む息苦しさを抱えており、病の不条理や心の傷をラジオで話してくれました。その実像を、できるだけ歪めないように伝えることが「ぽつラジオ」での私の役割です。音源をSNSでシェアすると、身近な人たちがてんかんに対する理解を徐々に深めてくれました。ドキュメンタリーの編集を依頼してくれたのも「ぽつラジオ」を聞いてくれた友人です。 『梅切らぬバカ』の現場では、一部のスタッフにてんかんのことをお伝えしました。発作のリスクを共有できるだけでもありがたいのですが、「作品のためですから遠慮はなしです」と、演出に集中できる環境を整えていただきました。これも大きな変化です。てんかんに対する偏見は、自分の中にあったのかもしれません。
- ――「梅切らぬバカ」というタイトルに込めたものは?
- 先ほど話したドキュメンタリーでは、男性の自宅の庭に立派な桜の木がありました。しかし、隣家の敷地に散ってしまう落ち葉のために苦情が届き、仕方なく伐採する場面があります。「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という諺がありますが、その家は桜を切ってしまった。切らざるを得なかった現実を認めつつ、本作では別の可能性を探りたい。もう一つの現実を描きたいという思いを込めています。 不要な枝は切らなきゃ駄目だというけれど、結局何が不要なのか、現実を梅の木に置き換えると、分からなくなっていく。人と関わっていく難しさに悩み、間違って切り落としてしまう枝もあると思います。そんな失敗や、よい方向に向かっていくプロセスを感じ取ってもらいたいです。